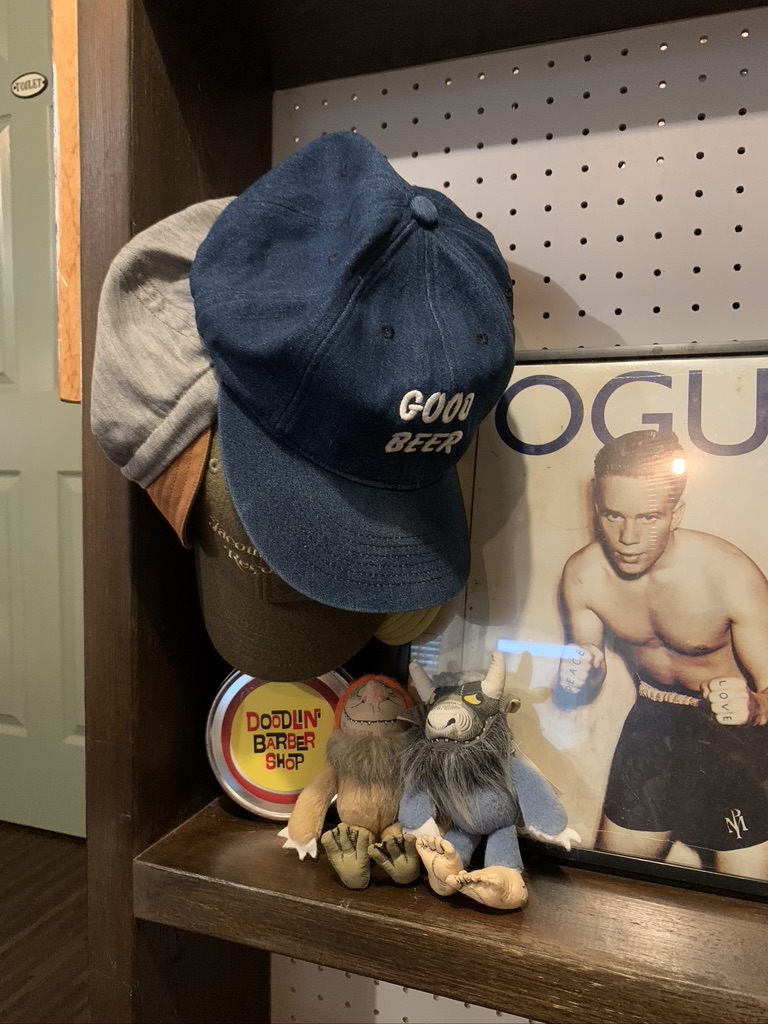外は今、晴れたとまでは言わないが久しぶりに雨が止んでいて、なんだかそれだけで心が緩むのです。
自分の幼少時、10月と云えば「日本晴の下での運動会」ってイメージなのですが、ここ最近の10月は毎年雨ばかりな印象。
毎度毎度子どもの運動会がやるのかやらないのどっち?でヤキモキ振り回されるって感じになってて、10月ってこんなだったっけかな〜って違和感。
気になったので、私が小学生だった1978年〜1983年の10月の天気を調べてみましたら、私の印象通り断然晴れが多く、雨天はだいたい4、5日しかありませんでした。
ほら、私の印象は正しかった。
ってことはだ。
いつから、関東の10月が雨が多くなったのでしょうか……
今から調べようと思えばチチンプイプイなのですが、やめておきます。
ナゼ?
面倒臭いからです。
うふふ。
違和感と云えば、最近久々に読み直したマンガ『三億円事件奇譚 モンタージュ SINCE 1968.12.10』(渡辺潤著)なのです。
相変わらず、とても面白く手に汗握らさせていただいたのですが、やはり週刊誌に連載されていたからか、「続きはどうなる?早く読みたいぜ!」と思わせる「煽り」が多々ありまして。
この場面いる?この煽りどうなの?
いらないよね?
って感じちゃって、一気に興醒めさせられることがしばしば。
週刊誌連載時には、それで良いと思いますが、単行本化する際に加筆訂正できないものかと。
ちゃんとね。
ちゃんと、そこを物語がスムーズに繋がるように描き直している漫画家さんもいましてね。
こういう作品ならば、よりそこに気持ちを込めていただけたなら嬉しかったな〜と一読者、一ファンの床屋のオッサンは思ったのでした。
過剰な煽りにチリチリしてしまうようになってしまいました。
若かりし頃はうまく受け流せたのにな〜
違和感とか面倒臭いですよね。
頭の固いオッサンテイストで。
あ、先日観た映画『ホテル・ムンバイ』がとても良かったです。
スリリングでありながらも社会派でありメッセージ性も強く、考えさせられるような作品。
すなわち私の好みです。
こんなに映画でハラハラドキドキさせられたのは久しぶりなんじゃないかな。
21世紀に突入してからは初めてかも。
まぁそんなわけで、今日は定休日。
シッカリ休もうと思います。
股旅。